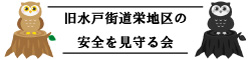キャンペーン連載「残土の闇 警告・伊豆山」など
日本新聞協会は7日、2022年度の新聞協会賞を発表した。静岡新聞社のキャンペーン連載「残土の闇 警告・伊豆山」と一連の関連報道(熱海土石流取材班 代表・豊竹喬熱海支局長)など6件が選ばれた。授賞式は10月18日、山梨県富士吉田市で開かれる第75回新聞大会で行われる。
「残土の闇」は、21年7月3日に熱海市伊豆山で発生し死者27人、行方不明者1人を出した大規模土石流災害に関し、信仰の地だった伊豆山に土砂が盛られた経緯や土地所有者の業者と行政の“攻防”、土石流を目の当たりにした発災当日の住民や行政の動き、犠牲者遺族の苦しみ、復興を目指す被災者らの取り組みなどを全36回の連載で追った。
発災直後から60人を超す記者が県内各地から交代で現地に入り、連載の基礎となる多角的な取材を重ねた。
日本新聞協会は授賞理由を「地元紙が総力を挙げて災害の原因を究明し、各地に潜む同様の危険性に警鐘を鳴らした企画報道として高く評価される」などとした。
本年度の新聞協会賞には49社97件の応募があった。静岡新聞社の受賞は初。20年度に新聞技術賞と新聞経営賞が分離・再編される以前の新聞協会賞では、技術部門、経営・業務部門で合わせて3度受賞している。
熱海土石流「残土の闇 警告・伊豆山」【連載全記事まとめ読み】一部
序章 子恋の森の叫び
①わが子守り 命落とした娘 奪われた「家族の未来」
「娘は殺された。母親と過ごせたはずの孫の未来も奪われた」。悲しみ、怒り、疑念-。複雑に絡み合った感情は、半年という月日ではとても整理できない。小磯洋子(71)は、ほおを伝う涙をぬぐいながら声を震わせた。母と娘、娘と孫を引き裂く悲劇に至るまで重ねられた不条理の数々に、納得できる答えは一つも見いだせていない。
娘の写真を見返しながら無念の思いを語る小磯洋子(左)と夫、栄一=22日、神奈川県湯河原町 夫、栄一(74)との間に生まれた西澤友紀=当時(44)=は7月3日、熱海市伊豆山を襲った土石流に命を奪われた。部屋の中に押し寄せた大量の土砂から必死に5歳のわが子を守り、帰らぬ人となった。
友紀の一家は2年前、「お母さんの近くで暮らしたい」と川崎市の一軒家を売却し、両親が暮らす実家から徒歩2分のアパートに移り住んだ。洋子と友紀は互いを頼り、何をするにも一緒。「双子のような親子」だった。
あの日、友紀は洋子に一本の電話をかけていた。「近くの小屋が流された。どうしよう」「怖かったらうちにおいで」。それが最後の会話になった。2人とも、約1キロ上流で異変が起きているとは気付きようもなかった。
熱海市に土石流発生の通報があったのは午前10時28分。アパートに土砂が到達したのは、それから25分以上後とみられる。数メートルの差で自宅の被害を免れた洋子が、娘を助けに行こうとしても、既に近づける状況ではなかった。「なぜ誰も『逃げろ』と言ってくれなかったのか。サイレンでも大声でもいい。1分もあれば十分逃げられたのに」。友紀が住んでいたアパートでは5人が死亡した。
その後の報道などで土石流の起点は「盛り土」とは名ばかりの残土処分場だったことが分かった。「市の職員も市議もその存在を知っていたはず。なのに、ほとんどの住民は知らされていなかった」。洋子の疑問は疑惑に変わっていった。「危険と知りながら伝えなかったのには何か裏があるのでは」
洋子は今、この土石流の最も幼い遺族であろう5歳の孫の世話をしながら神奈川県湯河原町の応急仮設住宅で暮らしている。母親を失った孫は、笑顔が減り、一時は幼稚園に通えなくなった。
ある日、孫がぽつりと友紀の夫である父親に言った言葉が洋子の胸に突き刺さった。「土石流は怖かったけど、野菜を頑張って食べるから、パパ頑張ろう」。孫は残酷な現実を懸命に受け止めている。
「この子が誰にも遠慮することなく、自立した考えが持てるようになるまで守らなければ」。あの日以来、洋子は不眠が続いている。「ぎりぎりの精神状態」だが、不条理に満ちた娘の死の原因と責任を明らかにしたいとの思いが消えたことはない。友紀が守り抜いたこの5歳の子のためにも。(文中敬称略)
◇
26人が死亡し、1人が行方不明になっている熱海市伊豆山の大規模土石流。被災地付近には「子恋(こごい)の森」と呼ばれる森林が広がる。遠くから見ると、母親が赤子を抱いて寝ている姿に見えることから、先人が名付けたと伝えられる。ずさんな工法で造られた盛り土による「人災」と指摘される土石流は親子や夫婦を切り裂き、平穏な日常を奪った。あの日から悲しみと怒りを抱えることになった遺族を追った。
②里帰り中、夫の悲報 40年の歩み 別れは突然
紅葉した木々の葉が残る12月中旬、小川慶子(71)は1人で暮らす熱海市伊豆山の応急仮設住宅でスマートフォンを見つめていた。画面に映るのは7月の大規模土石流で犠牲になった夫の徹=当時(71)=と3年ほど前に撮った思い出の一こま。「楽しい日々はもう来ない」。あれから半年。今も絶望の淵にいる。
土石流で犠牲となった小川徹(右)に寄り添う妻、慶子。3年ほど前に撮影した思い出の写真 突然の悲報だった。7月3日午前、慶子は沖縄県南城市に里帰りしていた。電話が鳴り、耳元に響いたのは知人の緊迫した声。「どこにいるの? 土石流で旦那さんが行方不明だから早く帰ってきて」。耳を疑い、一瞬、息が止まった。
徹は土石流の数分前、長雨を心配する慶子と2人の娘に無料通信アプリで「雨かなり強いけど伊豆山は何でもないよ」とメッセージを送っていた。その直後の惨事を知る由もなかった。
「うそであって」。慶子はそう願いながら飛行機に飛び乗った。しかし、翌日着いた伊豆山の自宅は既に跡形もなく、周囲は黒い土砂に覆われていた。徹は発災から15日後、土砂とがれきの中から変わり果てた姿で見つかった。
40年以上連れ添った夫は「唯一無二」の存在だった。出会いは20代前半の頃、偶然居合わせた都内の喫茶店。背が高く、純朴な性格の徹にひかれた。2人はすぐに意気投合し、結婚を機に徹の生まれ故郷の熱海で暮らし始めた。2人の子宝に恵まれ、家事も育児も夫婦で常に支え合った。
子煩悩な徹は、長女が1歳の時、立って歩いている姿を見て涙を流しながら喜んだ。その姿が脳裏に焼き付いている。授業参観や運動会などに積極的に足を運び、わが子の成長を何よりも生きがいに感じていた。
娘たちは独立し、孫も生まれた。古希を迎えたころ、慶子は徹にこう話した。「いつか欧州に旅行に行きたい。これからは楽しいことばかりだね」
そんなおしどり夫婦に、何の前触れもなく襲いかかったあの夏の悲劇。慶子と娘たちは、趣味のギターを奏でながら歌う徹の表情や日常の何げないしぐさを毎日のように思い出す。「大切な人を奪われ、悲しみと怒りで胸が砕けそうになるの」。いまだに現実を受け止められず、声を詰まらせる。
11月、慶子は娘を失った小磯洋子(71)らとともに刑事告訴人になり、盛り土を含む土地を2011年まで所有し盛り土を造成した神奈川県小田原市の不動産管理会社の代表(71)と現在の土地所有者(85)に対する殺人容疑の告訴状を熱海署に提出した。その日、慶子が胸に抱いていた徹の遺影にはこんな言葉が書き添えられていた。「通報はなかった 何も知らずに 土石流に呑(の)まれ あなたはいない」(文中敬称略)
③母失った悲しみを力に 「人災」確信、闘いを決意
12月上旬、神奈川県小田原市の市民交流センターの大会議室は超満員だった。同市の有志が企画した危険な盛り土をテーマにした講演会。熱海市伊豆山の大規模土石流で母の陽子=当時(77)=を亡くした瀬下(せしも)雄史(53)=千葉県=は聴衆にこう訴えた。
不適切な盛り土を造成する悪質業者に立ち向かう決意を語る瀬下雄史=12月上旬、神奈川県小田原市 「無能な行政とおとなしい住民が重なったところに悪質業者がはびこる。だからこそ、団結して悪に毅然(きぜん)と対応することが必要なんです」
雄史は8月に発足した「熱海市盛り土流出事故被害者の会」の会長として、約70人の遺族、被災者の先頭に立って行動してきた。講演活動はこの日が初めて。「伊豆山の悲劇を繰り返させない」。遺族の悲しみや怒りだけでなく、強いメッセージを発する狙いがあった。
雄史は横浜市育ち。伊豆山は約20年前、両親が海の眺望を気に入って移住した地で、自身も月に1度は訪れていた。7月3日、両親の家は土砂にのみ込まれて倒壊。母は発生22日後に死亡が確認された。パーキンソン病とがんを患い入院していた父はその約1カ月後、他界した。「苦しむだけだから」と、母が先に旅立ったことは最後まで伝えなかった。
母の死が判明するまでの間、雄史は起点の盛り土に問題があったとの証言を複数の住民から得た。「人災だ」。そう確信し、造成業者の責任を追及する決意をした。ただ、一人で闘える相手ではないことは想像できた。「世論を味方に付けて数の力で闘おう」。独自に被害者の会の草案をつくり、避難所で配布して同志を募った。
悲しみと怒りを原動力に雄史は8月、遺族の先陣を切って盛り土を含む土地の現旧所有者を業務上過失致死容疑などで刑事告訴。県警は強制捜査に乗り出した。被害者の会は9月、両者などに約32億円の損害賠償を求める民事訴訟を起こした。
ずさんな工事の末に積み上がった盛り土。その危険性を認識していた熱海市や県にも不信感はある。「もし住民に周知していたら、反対運動を起こすなどして造成業者を追い出せた」。現時点で行政訴訟を起こすかどうかは決めていないが「行政に不備があったことを前提に総括すべきだ。その上で再発防止や復旧復興を語ってほしい」と語気を強める。
全国にまん延する残土の闇。その構図は伊豆山と全く同じだと指摘する。行政指導を無視して土砂の投棄を繰り返したまま姿をくらます造成業者。その経緯を知らないと言い張る新たな土地所有者。両者に手を下せない行政。そして、危険性を知らされない住民-。「悪質業者が暗躍できない社会をつくるために、声を上げ続けることを忘れないで」。雄史の呼び掛けに、多くの聴衆が共感した。(文中敬称略)
第1章 変わりゆく聖地
④平安から続く信仰の場 修験の道、断たれた陰で
2021年7月3日、大規模土石流に見舞われた熱海市伊豆山。この地は平安時代から山岳修験霊場として栄え、山腹から湧く湯が海岸に向かって急斜面を走るように流れ出ていたことから「走湯山(そうとうざん)」の名でも知られる。多くの修行僧が信仰を寄せた“聖地”は、伊豆に流されていた若き日の源頼朝が北条政子と忍び会い、源氏再興を誓った地でもある。
末代上人の供養塔で、太田佐江子さんの冥福を祈る歴史愛好仲間=1月下旬、熱海市 「母は誰よりも伊豆山の歴史を誇りにしていた」。そう振り返るのは土石流で犠牲になった太田佐江子さん=当時(93)=の長女酒井真理乃さん(66)。太田さんは5年ほど前に亡くなった夫君男さんと共に長年、郷土史の伝承に取り組んだ。趣味で収集した膨大な史料を自宅に保管し、市に寄贈したこともあった。「熱海の歴史文化と教育の振興に情熱を注いでいた」
太田さんがとりわけ強い関心を寄せたのが富士登山の開祖とされる「末代上人(まつだいしょうにん)」だった。平安時代後期、現在の伊豆山神社と般若院が一体となっていた伊豆山権現で修行を重ね、噴火を繰り返す富士山を鎮めるために経文を山頂に埋納し、富士山信仰の礎を築いたと伝えられる人物だ。
06年、末代上人の供養塔が熱海市最北部の日金山で発見されたのを機に、太田さんは夫婦そろって地域の歴史愛好者の団体「富士山と末代上人 熱海の会」の発足に尽力した。13年の富士山世界文化遺産登録に向け、同団体の副会長として末代上人の功績や富士山と伊豆山の深いつながりをユネスコ(国連教育科学文化機関)や文化庁に熱心に発信した。
長年にわたって活動を共にした会長の真鍋梅美さん(80)は「伊豆山を愛していたのに、なぜ土砂に巻き込まれてしまったのか。本人が一番悔しいはず」と太田さんの無念を推し量る。違法な人為行為によって聖地は傷つけられ、「先祖代々、皆で守り続けてきた歴史文化も軽んじられた」と憤りを隠さない。
真鍋さんは数年前、妙な異変を感じていた。伊豆山の山中には修行僧が通ったとされる富士山に通じる修験道が幾つも残されているが、ある時、その修験道の所々が開発業者によって相次いで通行禁止にされた。「一体、誰が何をしようとしているのか…」。言い知れぬ不安が胸をよぎった。
その陰で、後に大規模土石流につながる乱開発が進められているとは、このときは思いもしなかった。
◇
熱海市伊豆山の住民は、約1300年前に発見されたとされる日本三大古泉の一つ「走り湯」や山岳修験に象徴される長い歴史と豊かな自然に誇りを持っている。悲劇から間もなく8カ月。地域の営みを支えてきた自然はいかに変貌していったか。時をさかのぼる。
消えた「70年前の災害」 「安全なまち」の過去に…【残土の闇 警告・伊豆山⑤/第1章 変わりゆく聖地②】
熱海市伊豆山の集落を流れ下る逢初(あいぞめ)川の流域は走り湯を生むほど急峻(きゅうしゅん)な地形でありながらも、信仰の地として栄えた平安時代からの長い歴史の中で大きな土砂災害や水害に見舞われた記録は少ない。「ここは地盤が強いから安全」「災害とは無縁の地」。これが住民の共通認識だった。
戦前に撮影された伊豆山の風景。水車が回り、水が豊かな地であることを物語っている(「熱海を語る 明治・大正・昭和写真史」より) 戦前や戦後間もない時期に撮影された伊豆山の風景写真には、丹念に手入れされた棚田や勢いよく回る水車などが捉えられている。いとこの太田洋子さん=当時(72)=や幼なじみの小川徹さん=当時(71)=を土石流で亡くした高橋薫さん(72)は「昔は牛舎があって川の水で牛乳を冷やしていた。山から湧き出る水で地域の生活用水は賄われていた」と振り返る。
地域を潤し、のどかな風景の中心を流れていた逢初川は住民の原風景でもあった。数十年後、源頭部に積まれた盛り土から大量の土砂が崩れて流れ下り、集落に襲いかかることになる。高橋さんは「どうしてこんなことになったのか。盛り土が憎いし、悔しい。伊豆山はこれからどうなっていくのか」と唇をかんだ。
「安全地帯」-。住民にそう信じ込まれていた伊豆山だが、高橋さんより年配の住民の男性(84)はこう証言する。「今から70年ほど前、今回と同じような場所で小さな土石流が起きたことがあった。でも、ほとんどの人がそのことを知らない」
男性によると、当時小さな土石流が起きた現場は2021年7月3日の土石流で最も早く流された住宅の近く。150メートルほどにわたって土砂が流れ、田畑が埋まったものの、人的被害はなかったという。男性は記録を探したが、見つけることはできなかった。住民の間で語り継がれずに風化してしまったのか、やがて逢初川上流部には住宅が立ち並ぶようになった。
「ここは昔、土石流があった場所だ」「あの山には(地下水が流れる)“ミズミチ”がいくつも通っているんだ」。男性は、上流部に家を建てようとする人や市に警告した。走り湯の伝説を生み出した伊豆山の急峻な地形と豊富な水。川筋に大量の土砂がたまりさえすれば、走るように流れ下る恐れがあった。
知らずに家を建てた人には何の落ち度もない。それでも、少しでも災害の記憶と記録が継承されていればこれほどの大惨事に至らなかったのではないか-。男性は悔やむ。「そんな危険をはらんでいた場所にずさんな盛り土を造成した悪質業者と、その工事を止められなかった行政は取り返しの付かない過ちをした」